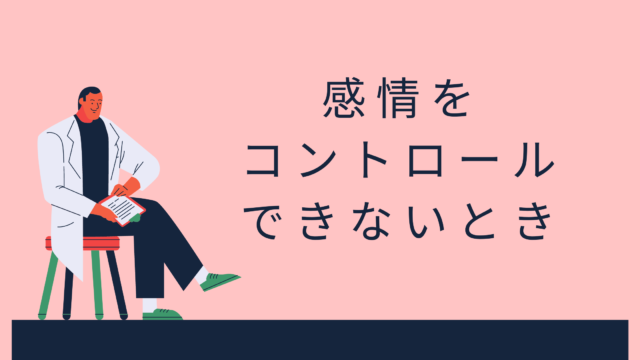こんにちは、まじめちゃんです。
みなさん、哲学書って読みますか?
なじみのない方が多いのではないでしょうか?
私も哲学書そのものにいくつか挑戦したことがありますが、挫折しました。
つまらない、難しい、古い、役に立たない…
そう思っている方に、オススメしたい入門書を紹介します。
史上最強の哲学入門書!
巷に「哲学入門書」は多々ありますが、この飲茶さんの『史上最強の哲学入門』は、その名の通り、史上最強です。
そもそも、なぜ哲学書はつまらないのでしょう?個人的には、以下の2つが原因だと思います。
- 難しい、分かりづらい用語が使われている
- 何がどうしてそういう考えに至ったのか不明
まずは一つ目として、用語の難しさがあります。
よくある入門書は入門書なのに、ある程度哲学用語を知っている前提で書かれていますが、この本は違います。
わかりにくい専門用語はまったく使われていません。
それどころか、はじまり(の一部)はこんな感じです。
せっかく書く機会を得たのだから、今までにない「史上最高の哲学入門書」を目指して書くべきではないか!では、どうすればいい。今までの哲学入門書には何が足りなかったのだろうか?
結論を先に言うなら、「バキ」分が足りなかったのです。
え?バキ…?そう思った方、その反応は正常です。
でも、面白そうではないですか?
作者の飲茶さんいわく、格闘家と哲学者は、格闘家が強さに一生をかけた人間たちであるように、哲学者も強い論(誰もが正しいと認めざるを得ない論)の追求に一生を費やした人たちであり、似ているのだそうです。
この本は難しい用語は一切使われていないどころか、バキのごとくシンプルにそれぞれの論を戦わせています。
そして、二つ目ですが、この本ではいくつかのテーマに沿って、誰がどのように論を発展させてきたのかを時系列で説明してくれています。
例えば、国家という考え方について、まず〇〇がこういう論を作り上げて、その数百年後に××が〇〇の論のこういうところが違うと思い、別の論を作り上げて…
といったような感じです。
よくある入門書は、誰か一人にフォーカスしていたり、テーマを設定せずただ古代ギリシャから現代までをなぞったような内容が多いですが、それに比べると圧倒的に読みやすいです。
哲学書を読むべき理由
そもそも難しそうで、役に立たない古臭い哲学書を何で読む必要があるの?
そう思うかもしれません。
私は哲学書は、読者の思考の扉を開いてくれるからだと思っています。
誰もが忙しい毎日を過ごしています。
似たような日々の繰り返しで、似たような思考をたどることが多く、考える範囲も、学校のこと、家族のこと、仕事のことなど、限られているのではないでしょうか。
でも、この混迷の時代、将来のことなんて見通せない難しい時代、生き抜くために必要なのは考える力ではないでしょうか?
何が起きても、きちんと自分で考えて、納得し、決断する力、それが必要ではないでしょうか?
とはいっても、そんな力を自力で育てるのは困難です。
そんな時、哲学書と哲学者たちの生き様が役に立つのです。
彼らの考え方やその論に至った経緯は、私たちとは違うステージから世界をみていたような気持ちにさせられます。
忙しい日々からふっと抜け出して、もっと俯瞰的に、考える力を養うのに哲学はうってつけだと思うのです。
また、この本はあくまで入門書です。もしこの中からこの哲学者の話をもっと知りたいと思ったら、自分で調べたり、より専門的な本に手を伸ばしてみるのがいいと思います。
お子さんへのプレゼントにもオススメです。